この記事では、外国人が日本で仕事をするためには、どのような資格があるかを解説していきます。

外交
この在留資格は、外国政府の大使館員等として働くための在留資格です。または、その家族の人に与えられます。
公用
外国人で公務により日本にいる人、もしくはその家族に与えられます。
教授
内容
日本の大学、短期大学又は高等学校の学長、教授、准教授、常勤講師、助手などの活動。日本の大学が外国人講師を呼び寄せるケースや、外国人技術者などが日本の大学で講師として採用されるケースなど。
この資格は、大学などから報酬を受ける場合に該当します。報酬を受けない場合には「文化活動」になります。
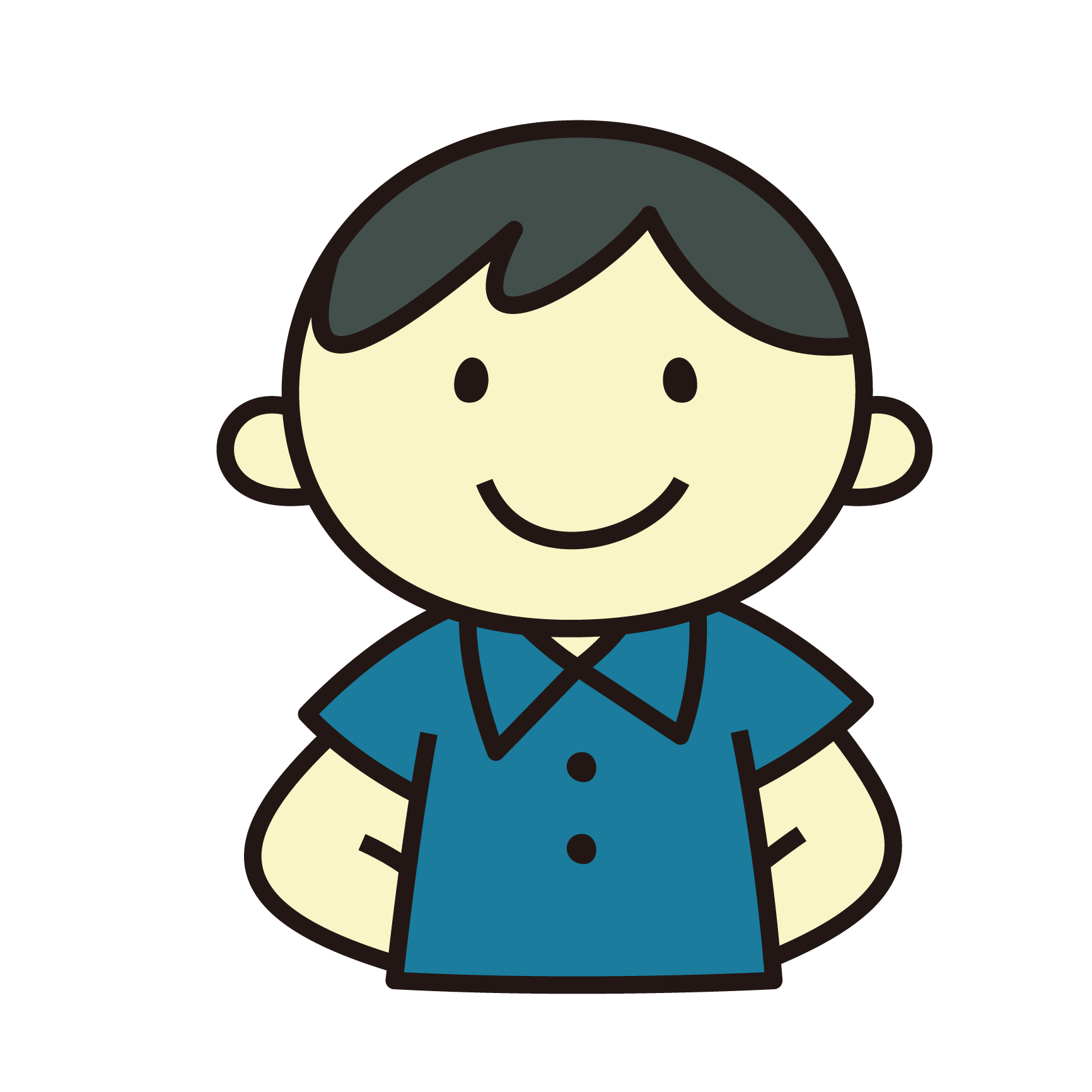 ビザ君
ビザ君学校の先生の資格なんですな。
 先生
先生主に大学で教える教授などの資格で、小学校や中学校で語学を教える先生は「教育」の資格になり、民間の語学学校で教える講師の資格は「技術・人文知識・国際業務」になるよ。
芸術
収入を伴う、音楽・美術・文学その他芸術上の活動。
大学等において研究の指導や教育を行う場合には、在留資格「教授」に該当します。
収入を伴う活動をしない場合には「文化活動」に該当します。
「芸術」に該当するためには、展覧会入選などの相当程度の業績があることが必要になります。
宗教
外国の宗教団体から日本に派遣される、宗教家の行う布教活動をする在留資格です。
外国人僧侶が日本の寺院に派遣されたり、外国人牧師が日本の協会に派遣されて、布教活動や宗教活動をするなどが代表的な事例です。
報道
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道活動をするための在留資格です。
海外通信社の日本支社に外国人記者を呼ぶ、フリーのカメラマンと外国の報道機関が契約して招聘するなどが代表的事例です。
日本の報道機関との契約は「報道」には該当しません。
高度人材
高度専門的な能力を有している人で、この資格に該当する人は、最初から5年の在留期間が取得できたり、親の帯同が許可されたりなど優遇処置がかなりあります。
高度専門職1号(イ)
日本の公私の機関と契約に基づいて行う研究、研究の指導・教育などの活動。
高度専門職1号(ロ)
日本の公私の機関と契約に基づいて自然科学、人文科学の分野の知識、技術を要する業務に従事する活動。
高度専門職1号(ハ)
日本の公私の機関において貿易その他の事業の経営もしくは管理する活動。
高度専門職は、点数制になっていてそれをクリアすることにより高度専門職の資格を取得することができます。
経営・管理
日本で会社の経営もしくは管理をする在留資格です。
会社を自分で設立し経営していくには、この資格を取得する必要があります。また、企業に取締役として外国人を招聘するのにもこの在留資格を取得して招聘します。
「技術・人文知識・国際業務」や「技能」にくらべると学歴要件などはありません。しかし、その分会社設立後の計画などは厳しく審査されます。
「経営・管理」の取得要件については、後日詳しく別の記事で紹介いたします。
法律・会計業務
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うとされている法律または会計に係る業務に従事する活動です。
具体的には、弁護士、司法書士、土地調査家屋士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士または行政書士の資格でこれらの業務に従事する活動に該当します。
医療
日本の医療関係の資格を持ち、具体的には、医師、歯科医師、薬剤師、保険師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨朱工学技士又は技士装具士の資格を持ち、これらの業務に従事する活動に該当します。
研究
日本の研究機関で研究する人と一般企業で基礎的・創造的な仕事をする人がこの資格に該当します。
一般企業で業務遂行に直接資する場合には「技術・人文知識・国際業務」に該当します。
要件
大学を卒業しもしくはこれと同等以上の教育を受けた後、従事しようとする研究分野において修士の学位もしくは3年以上の研究の経験を有し(大学院において研究した期間を含む)ていること。または、従事しよようとする研究分野において10年以上の研究の経験があること。
日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けること。
教育
日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校等の教育機関における教育活動が該当します。
外国人の英会話講師として勤務する場合などが当てはまります。
要件
次のいずれかに該当すること
- 大学を卒業しているか、大学と同等以上の教育を受けていること
- 行おうとする教育に必要な技術又は知識に関する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと。
- 行おうとする教育に関して免許を有していること
外国語の教育をしようとする場合は、その外国語により12年以上教育を受けていること。それ以外の科目の教育をしようとするときは、その教育について5年以上従事した実務経験を有していること。
日本人と同等以上の報酬を受けること。
技術・人文知識・国際業務
日本の公私の機関との契約に基づいて行う
- 理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務。
- 法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務。
- 外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動。
要件
自然科学または人文科学の分野の技術・知識を必要とする業務に従事する場合は次のいずれかに該当すること
- その技術もしくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、または同等以上の教育を受けていること
- その技術もしくは知識に関連する科目を専攻して日本の専門学校を修了していること
- 10年以上の実務経験(大学、高等学校、専門学校等の専門分野の学習期間も含まれます。)を有すること。
外国の文化を基盤とする思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合は、次のいずれにも該当すること
- 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外の取引業務、服飾もしくは室内装飾のデザイン、商品開発その他これらに類似する業務
- 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳、通訳または語学の指導に関する業務に従事しようとするときは経験は不要です。
いずれも、報酬は日本人と同等以上の報酬が必要です。
この在留資格についても、後日詳しく別の記事でご紹介する予定です。
企業内転勤
外国の日本企業の子会社、関連会社から日本の本店・支店に転勤する場合、外国の企業から日本にある海外企業の子会社、営業所などに転勤する場合が該当します。
要件
- 海外において、外国に本店支店などで1年以上「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に携わっていたこと。
- 日本人と同等以上の報酬を受けること。
興業
演劇、演芸、歌謡、舞踏、演奏、スポーツなどの興業のため来日する在留資格です。
技能
日本の公私の機関と契約して、産業上特殊な分野に属する熟練した技能を持った業務に従事する活動です。
要件
料理の調理又は食品の製造の技能で外国において考案されたもの。
例 中華料理のコック、インド料理のコック
10年以上に経験(外国の教育機関においてその調理や製造に関する科目を専攻した期間も含みます。)
外国に特有な建築土木に関する技能
10年以上の実務経験(外国の教育機関において、その科目について履修した期間も含む)
外国の特有な製品の製造又は修理に関する技能
10年以上の実務経験(外国の教育機関において、その科目について履修した期間も含む)
宝石・貴金属・毛皮の加工に関する技能
10年以上の実務経験(外国の教育機関において、その科目について履修した期間も含む)
動物の調教に関する技能
10年以上の実務経験(外国の教育機関において、その科目について履修した期間も含む)
石油探査のための海底掘削。地熱開発のための掘削、海底鉱物探査のための海底地質調査に関する技能
10年以上の実務経験(外国の教育機関において、その科目について履修した期間も含む)
航空機に関する技能
250時間以上の飛行経歴
スポーツの指導に関する技能
3年以上の実務経験(外国の教育機関のおいて、その科目を専攻した期間及びプロ選手としての期間も含まれます。)または、オリンピックや世界選手権などの国際大会に出場した経験がある人。
ぶどう酒の鑑定(ソムリエ)に関する技能
次のいずれかに該当する人
- 国際ソムリエコンクールにおいて、優秀な成績を残した人。
- 出場者が、1国につき1名に制限されている国際ソムリエコンクールに出場した経験がある人。
- ワインの鑑定について、国または地方公共団体等の認定する資格を有する人。
技能実習
日本の技術や知識などを習得して母国に帰国後活用して、その国の活動に寄与するための在留資格です。この資格に関しては、別の記事で詳しく書いていきます。
まとめ
以上が、外国人が日本に来て仕事をするための在留資格です。これらの資格は基本的には、その資格の範囲の仕事しかすることができません。
たとえば、外国人コックとして日本に聞いている外国人がそのお店でもっぱらホールの仕事をすることはできません。また、企業内転勤で日本において、コンピューター関連の仕事をしている人が、その会社を退職して全く別の会社で同じようなコンピューター関連の仕事をするためには、資格を「企業内転勤」から「技術・人文知識・国際業務」に変更しなければ日本に在留し続けることができません。
次回では、これ以外の在留資格についてご説明します。

